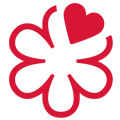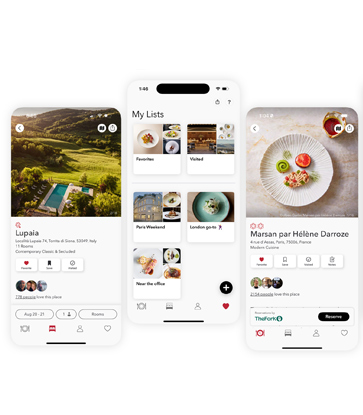年魚
鮎の一生は短く儚い。「年魚」と呼ばれるのは一年しか生きないため。生まれた稚魚は、水流に身を委ねて水温の高い海へと下り、厳しい冬の寒さをしのぐ。春から夏にかけて河川を遡上。夏の間は川の中流にある藻類を食べて成長し、秋を迎えると下流で産卵して寿命を迎える。鮎は一年を通して季節を表す季語でもある。春の若鮎、夏の鮎、秋の落ち鮎、冬の氷魚(ひうお)。昔から鮎を季節の便りとして食してきた。
喧嘩魚
涼しげな顔つきでありながら気性は荒い。主食とする藻類を確保するため餌場に縄張りを持ち、他の鮎が侵入すると攻撃する。喧嘩っ早い気性から「喧嘩魚」と名付けられた。この習性を利用するのが友釣り。おとり鮎の鼻に掛け針を仕込み、泳がせることで喧嘩を仕掛けてきた鮎を釣る。鮎で鮎を釣ることを「友」に例えるのが面白い。「喧嘩するほど仲がいい」のは、川の世界も同じのようだ。
奈良時代より伝わる「鵜飼い」という伝統漁も独特。世界でも珍しいこの漁法は、鵜を飼い慣らした鵜匠が操る。夜に小船を出し、舟首に立つ鵜匠が篝火で水面を照らす。驚き集まってきた鮎を、数羽の鵜に丸飲みさせて捕獲する。岐阜の長良川、愛媛の肱川、大分の三隅川を三大鵜飼いと呼び、夏を彩る風物詩。

香魚
鮎の味わいを「西瓜のような」「若草のような」と表現する。特有の青さを持つのはなぜだろうか。それは主食とする餌にある。清流の藻類を食べながら成長するため、爽やかで甘い香りを宿すのが「香魚」と呼ばれる所以。清らかな環境を好み、容姿の美しさから「清流の女王」「初夏の使者」とも称される。鮎は東アジア圏にしか生息しない。英語でSweetfishと名付けられたのは、西瓜を思わせる甘い香りから。
鮎料理
季節が待ち遠しい夏の涼味。待望の鮎料理を、東京・京都・大阪のミシュランガイド掲載店から紹介。祇園 丸山(日本料理/京都)
~鮎の塩焼~
日本の情景を映すのが京料理と説く丸山嘉桜氏。古来の風習と四季が織りなす献立に心を砕く。鮎は夏を告げる季語であり、日本料理に欠かせない。毎年献立に登場するのは六月頃。京都の鮎に塩を振り、炭でじっくり焼く。お供とするのが、たで酢。相性の良さから「鮎たで」と呼ばれるほど、なくてはならないもの。鮎が生息する川辺に自生しているのも不思議な縁を感じる。
チェンチ(イタリア料理/京都)
~鮎のフライ~
京都で育った坂本健シェフの料理観。その土地の食材をシンプルに表現するのがイタリア料理のイズムと語り、夏の京都に欠かせない鮎を料理する。試みたのは、和食の塩焼とは異なるアプローチ。鮎の身にニンニク風味の鮎のペーストを挟みフライにする。頭と骨は香ばしく揚げ、リコッタチーズがタルタルソース代わり。イタリア料理という枠組みを意識せず、昔からある素材の組み合わせを分解し再構築。
ラ・ベカス(フランス料理/大阪)
~鮎のリエットとビシソワーズ~
渋谷圭紀シェフが最も得意とする初夏の一品。四半世紀も前、日本料理店で鮎の背越しや塩焼を堪能していたとき、ふとひらめいたのが鮎のリエットだという。鮎を塩焼にして骨や内臓ごとフードプロセッサーにかけ、たっぷりのバターで焼く。夏らしく冷製スープのビシソワーズを合わせた。鮎とたでの相性に想を得て、洋素材のエストラゴンでアレンジ。
フジヤ 1935(イノベーティブ/大阪)
~高津川の鮎 ルッコラ~
舞台は島根県西部の高津川。夏の鮎は本能の赴くまま、遡上しながら上流へと向かう。栄養を蓄えるため、卵を宿すため、岩に張り付いた藻を必死に削り取りながら昇流する。感性豊かな藤原哲也シェフは、料理に鮎の生命力を投影した。鮎にまとわせた緑のパウダーは、藻に見立てたルッコラのソース。光を浴びたガラス皿は、清流の水面のように輝く。鮎への敬意、生命の儚さ、自然の美しさをメッセージとして表現した。
リューズ(フランス料理/東京)
~鮎のクルスティアン 焼きなすのピュレと共に 生姜とたでのアクセント~
和の食材をフランス料理に昇華させた夏のスペシャリテ。飯塚隆太シェフが念頭に置くのは、鮎を一尾丸ごと味わえること。三枚におろし、肝のペーストを身の内側に塗り、骨煎餅も挟む。それをパートフィローで包み焼に。頭から取っただしに、たでの葉を加えたソースは、鮎とたでの相性がヒント。頭から尻尾まで、鮎のおいしさが一皿に集約されている。
ラ クレリエール(フランス料理/東京)
~稚鮎のフリチュール クマ笹とクレソンのクーリ 南高梅のエミュルション~
フランス料理は地方料理の集合体と説く柴田秀之シェフ。東京を一つの地方ととらえ、四季の食材と日本人の感性を大切にする。鮎という日本特有の食材を扱うのも自然なこと。和食店で味わった稚鮎の天ぷらと抹茶塩をヒントに、フレンチの視点からレシピを編み出した。稚鮎はパートブリックで巻いて米油で揚げる。地元北海道名産のクマ笹茶をクレソンのクーリに練り込む。毎年鮎料理をつくりながらも常にアップデートさせてきた。
日本書紀に記述され、万葉集でも歌が詠まれるほど古くから愛されてきた鮎。天皇家との関わりが深く、鮎の占いが国の統治を左右するほどだったという。建国の神話にも登場し、縁起の良い魚として重宝されてきたと聞けば、ありがたい食べ物に思えてくる。鮎が旬を迎えるのは夏。香ばしく焼いた塩焼には冷えたビールが合う。双方の苦味が呼応し、暑気払いとなるだろう。
関連記事:
ミシュランガイドフォーカス:春の食材「筍」
ミシュランガイドフォーカス:春の食材「蛤」
ミシュランガイドフォーカス:冬の食材「ふぐ」
Illustration image ⒸM Andy/Shutterstock