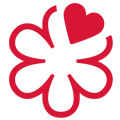地球上にある酸素の3分の2は海でつくられたもの。光合成といえば地上の植物を思い浮かべるかもしれないが、海中でも太陽の光と海の植物で酸素を生む。

ブルーカーボン
海は大気中の二酸化炭素を海面から吸収して温暖化を緩和している。海水に含まれた二酸化炭素を海藻などが取り込み、太陽の光を借りて有機炭素を生成。これが長期にわたり海底に貯留される循環を「ブルーカーボン」と呼び、地球温暖化防止に貢献している。
昆布の力
海藻の中でも昆布は大型のため光合成の効率が良い。杉と比較するならば、二酸化炭素の吸収量は5倍ほど。つまり植林するのと同じように、海に藻場を増やせば地球温暖化の減少につながる。それを目的に昆布の養殖を始めた地域も見受けられ、昆布が持つ可能性に期待が高まる。
環境を守る海の森
緑が茂る藻場の光景は“海の森”と呼ぶに相応しい。小魚のすみか、産卵場、餌場など、海洋生物の生活に役立ち、そこに生息する生物たちは有機物を分解して水質浄化も果たす。言い換えれば、昆布を取り巻く環境が循環することで生態系を守っているのだ。
昆布はサステナブルシーフード
昆布はすべて食べられるためフードロスがない。乾物にすれば長期保存も可能。カリウムやカルシウムなどのミネラルを豊富に含むため健康の持続にも優れている。また、農業にも貢献。未利用の昆布は家畜の飼料になるほか、畑の堆肥にすることで野菜が天然のミネラルを得られる利点がある。

昆布が切り拓く食の未来
古来、海に囲まれた日本は昆布を要に食文化を発展させてきた。2013年には「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで各国のシェフが昆布だしに注目。「うま味」をキーワードに、新たな味覚として料理に取り入れている。また、植物性であることから環境に負担をかけず、ヴィーガンやベジタリアンにも好まれる。

昆布が地球を救う
世界中の沿岸に海藻は生息するが、水温の上昇により減少している。海中でダンスをするように昆布が揺らめく姿は、人類にSOSのサインを送っているのかも。私たち一人一人が海を守るために何ができるのか考え行動に移せば、地球の未来は変えられるはずだ。大陸は分かれていようとも世界は海で繋がっているのだから。