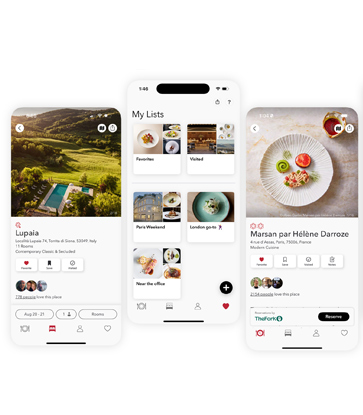都会の「デスティネーションレストラン」
2023年に誕生した虎ノ門ヒルズステーションタワーの最上階、近未来的なビルの専用エレベーターで到着する。駅直結でありながら、そこに訪れること自体が、一つのデスティネーションとなるレストランが「アポテオーズ 」。
エレベーターが開いた瞬間からふわりと包まれる香りは、北村啓太シェフの人柄をイメージし、檜の香りをベースにアロマセラピストが特別に調合したもの。香りは人の記憶を呼び覚ますもの、そしてフランス料理は香りの料理であると北村氏は考える。そして、ウェイティングでは、仁和寺で収録した虫の声、鳥のさえずりなどとピアノを組み合わせたオリジナルの音楽が出迎え、香りとあいまって、しずかな森にいるような、心を落ち着かせる時間が待っている。一息ついた後は、ダイニングルームへ。北村氏が「大好きな建築家」だというガウディ建築をイメージした重厚な扉が開くと、左右に厨房、正面に見事な東京の夜景が広がる。華やかな美食の舞台の幕開けだ。

パリから東京へ、高みを目指しての選択
シェフの北村啓太氏は、「ナリサワ/NARISAWA」 で研鑽を積み、2008年に渡仏。パリの三つ星「ピエール・ガニェール」などをへて、2区のフランス料理店「エール」のシェフに。日本に帰国する前の最後の5年間は、ここで一つ星を守り続けてきた。更なる星を目指す上で、何をすべきか。そんな折に舞い込んだ、東京・虎ノ門ヒルズステーションタワーの最上階という抜群のロケーションでのオファー。「エール 」の仲間たちと話し合った末に、チームを連れて日本への帰国を決めた。初年度、一つ星を得た。「もちろん嬉しかったです。でも、帰国したのはもっと上を目指すため」何が足りなかったのか。住み慣れたパリを離れ、この挑戦にかけてくれたスタッフたち。仲間のためにも、更なる研鑽を自らに誓った。

日本ならではのフレンチ
アポテオーズとは、フランス語で「最高の賞賛」という意味。日本の食材を中心に据え、最高の賞賛をおくるような料理を生み出したいと名付けた。日本でしか食べられない、日本らしさを最大限に表現するフレンチ。帰国後は日本の生産者をめぐり、食材の背景にある物語を吸収し、料理作りに反映してきた。日本の自然風土をより深く知りたいと、山梨県のハーブ生産者のナビゲートで、富士山麓の山に入るように。そこで気づいたのは、日本の野山で力強く生きる植物の香り。「フランス料理は、香りを大切にする料理」だからこそ、日本らしい料理の表現として、日本の野山の香りを取り入れようと決めた。「たとえば、セリ科の野草、大和当帰(やまととうき)は、薬草としても扱われているもの。独特の香りは、ラベージのようでもあり、フランス料理との親和性もいい」と、オイルにして料理に使ったり、食後のハーブティにブレンドしたりしている。

想像力の「余白」をつくる
料理は日々進化を続けるが、最近は料理名も大きく変えた。これまでは、食材名を並べたものだったが、「旅のはじまり」と名付けられたある日のアミューズは「秋の詩」「フランスが誇る…」「ジャガイモなのに」という詩的なもの。想像力をかき立てるネーミングをつけることで、何が出てくるのだろう?という期待感がふくらむ。そこで目指すのは、料理を媒体にした、記憶の交換だ。「例えば『秋の夕暮れ』というタイトルの料理。この名前から私が思い浮かべるのは、生まれ育った滋賀県の秋の田んぼの野焼きの香り。その情景を映すように、夕焼けの太陽のような真紅のビーツに、藁の薫香をつけました。もちろん、このタイトルから浮かべる景色は、人によって違うでしょう。それでも、作り手と食べ手の記憶がリンクする、その媒体に料理があるというのは、とても豊かなことだと思うのです」。想像力という余白を生み出すネーミングが、記憶を呼び覚まし、いま、目の前の料理が心に残るならば、それは未来の思い出につながってゆく。そんな、時空を超えた食の世界を生み出していきたい、と考えているのだ。

新しく多様性のある、未来に向けたファインダイニング
記憶を未来につなぐ食を。そう考える北村氏が気になるのは、未来の食。地球温暖化などの気候変化により、魚がとれなくなったり、従来の育て方では作物を育てることができなくなったり、廃業する農家も増えた。「ファインダイニングだからといって、同じ種類の魚、同じ部位の肉を使わなくてはならないのか、代用になる食材はないのか。私たちはもう一度考え直さなければならないと思うのです」と、高級食材といわれる種類や部位だけに偏った食材使いに警鐘を鳴らす。江戸時代はその脂が好まれず、捨てられることさえあったというマグロのトロは、今では最高級食材として高値で取引される。「高級食材」は、時代で変わることの好例だろう。「いわゆる高級食材でなくても、料理人の技でおいしさを引き出し、美食の価値を生み出すことができるはず」と考えている。
だからこそ、見慣れない食材を見つけると、すぐにオーダーして活用方法を考える。そんなアプローチだからこそ、一つのテイスティングコースに使われる食材は100を超える。いろいろな食材を多様に取り込む。それは多くの食材をバランスよく織り込んだ、会席料理の精神にも通ずるところがある。

多くのプロの力で、立体的なファインダイニングの体験を
偏らずさまざまな食材を使い、食の多様性を守るだけではない。さまざまなサステナブルな取り組みも行われている。例えば、根セロリの皮は鶏のブイヨンと共に炊き上げ、ソースとして利用することで無駄なく使いきる。
伝統文化を大切に受け継ぎたいと、使っている食器のほとんどが日本の作家にオーダーしたものだ。

何よりも、100もの食材を織り込んだコースを生み出すことが可能なのは、28席の客席に対して、厨房9人、サービス6人という充実のチームがあるからこそ。近年増えた「ワンオペ」や少人数での高級料理店、それにはそれの良さがあるとは認めつつも「フランス料理はもともと、手数の多い宮廷料理。大勢の手で生み出すオートキュイジーヌ(至高料理)を継承したい」という思いがある。「サービススタッフがいて、ソムリエがいて、シェフがいる。多くの視点やアプローチがあることで、さまざまなアングルから光が当たり、食体験がより立体的に感じられるはず」と考えるからだ。まるで謎解きのような料理名も、それをきちんと説明できるスタッフが揃っているからこそできることだ。

守りたいのは、五感を通して記憶を呼び覚まし、心を動かす豊かな食体験。15年ぶりに帰国した日本から、志を同じくする仲間と共に、情緒あふれる日本の風土に光を当て、みずみずしい感性で伝えてゆく。その先にきっと「アポテオーズ」最高の賞賛が待っていると信じて。