気候変動や社会課題が深刻さを増すなか、レストランは「おいしい」を超えた役割を担い始めている。「レフェルヴェソンス (L’Effervescence)」 はその営みを「サステナブル」の先にある「リジェネラティブ(再生)」へと進めてきた。エグゼクティブシェフ生江史伸の思想と歩みを前後編で紹介する。
食材調達や調理、社会との関わりといった実践を積み重ねた先で、レフェルヴェソンスが次に選んだのは「数値化による検証」だった。後編では、その歩みを示すインパクトレポートを取り上げる。
関連記事:【前編】はこちら>
数字で可視化する責任 ― インパクトレポート
2011年の震災、そして2020年のコロナ禍を経て、外食の社会的意義を問い直した生江シェフは、その思考を修士論文「外食が提供する価値に関する研究」にまとめた。学術的な整理を踏まえ、その次の段階として、日々の営みを数値で検証し、「どこが進み、どこに課題があるのか」を可視化する実務へと発展させたのが、年次のインパクトレポートである。
レポートでは、電力、水道、ガスの使用量を定点観測し、ゲスト一人あたりに換算して年ごとに比較する。そこから導かれる二酸化炭素排出量や、廃棄物の動向も追いかける。数値化によって、想定以上に進んでいた点と、期待に届いていない点が明確になり、次の行動の指針が生まれる。単なる掲示ではなく、毎年の比較と評価を通して改善を回すのが狙い。
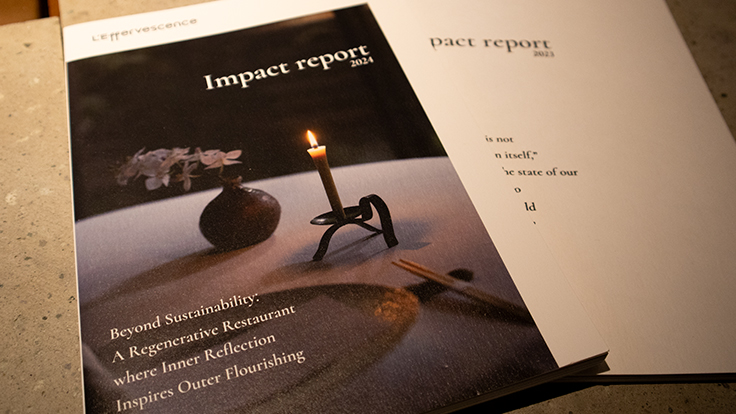
人の内面向けた可視化も重視している。外部の調査会社に依頼し、スタッフ全員にウェルビーイングサーベイを実施した。職場への帰属意識が高い一方で、自己実現に関する不安といったギャップも見えてきた。生産地への訪問や、課外活動が働く喜びにつながることなど、これまで感覚で捉えていた事柄が数値によって 確信へと変わった意義は大きい。
「ファインダイニングとして、行動の洗練を極めることは、料理やおもてなしの質を高めることと同じ線上にある」と捉える。インパクトレポートを発行することは、その歩みを社会へ約束する行為でもある。電力、水道、ガスといった光熱費から、二酸化炭素やウェルビーイングといった社会的な指標まで、目に見えにくいものを数値化し、次の一手へつなげていく。レフェルヴェソンスにとってのインパクトレポートは、そのための実務的な手段である。

思想としてのリジェネラティブ
近年、生江シェフが重視しているのが「リジェネラティブ(再生)」という考え方。サステナブルは「劣化をゼロに近づける営み」と例える。オゾン層の回復は、人の努力による改善の好例である一方で、海の酸性化や大気中の二酸化炭素はなお、増加傾向にある。こうした状況の中では、「ゼロに近づけることで満足するのではなく、プラスへ転じるような力を社会に蓄えていく」発想が必要だという。
この考え方の基点になっているのが、経済学者の下川先生が示す「自然を資本と考える」という視点である。水も土も皆で共有する“借り物”だとすれば、「借りたものを、利子を付けて返せているのか?」この問いに学びつつ、生江シェフはリジェネラティブを「借りを利子付きで返す営み」として語る。
思想は現場で具体化しつつある。すでに紹介したように、仕入れでは、再生型農法に取り組む生産者を優先し、収穫量の減少を価格で支え、未来へ続く選択を後押しする。調理でも、間伐材の薪の導入といった、森の多様性を守るエネルギーを選択している。
生江シェフは、「関わるすべてに借りを作らず、相手が喜ぶ形で返していきたい」と話す。料理やもてなしを磨くのと同じ線上で、環境や社会への働きかけをひとつずつ積み重ねる。その繰り返しがレストランの日常に「リジェネラティブ(再生)」の思想を定着させていく。

器づくりに込める再生の思想
レフェルヴェソンスはオープン以来、数年ごとに内装やキッチン、料理のスタイルを更新してきた。今年は「レストランとして貢献できる活動の精度を上げる」ことに軸足を置く。その考えをかたちにする取り組みが、現場で具体化している。
まずは、能登地震で工房や道具を失った輪島塗の漆芸家とのコラボレーションだ。レストランを象徴する蕪の料理に着想したもので、蕪から型をとって椀をつくる計画が進んでいる。単に器を新調するためではない。輪島や漆に目が向かうような話題を生み、現場の仕事の回復につながる動きを支えたいという意図がある。
また、十年ほど使い込んできたガラスの皿は、経年で細かな傷も重なっており、通常なら廃棄される。それを制作会社へ戻して粉砕し、再生ガラスとして新たな皿に作り替える。器や素材の使い終わりにどう向き合うかを、店の実務として検証する。こうしたレストランのゲストが見て感じることのできる再生的な取り組みをどのように表現していくのかが注目される。


社会との協働が拓く未来
レフェルヴェソンスの取り組みは、店の内側にとどまらず、公的機関、産業界、学術界との協働へ広がっている。現場の知見を社会に開き、実装の場と議論の場を行き来させてきた。
まず、公的領域での選出である。2024年、文化庁は食文化の功績者を顕彰する新制度の創設に向けて有識者会議を設置し、生江シェフ委員の一人に選出された。提言は翌年に公表され、制度化に向けた検討が進んでいる。
国際社会への発信としては、2022年の国連・世界海洋デーにおいて、ルレ・エ・シャトーを代表し国連本部でスピーチ。海藻の重要性と食の選択が海の健康に与える影響について、ホスピタリティ産業の立場から語った。
産業界との連携では、日本航空で機内食の監修を担うとともに、研修を通じてレストランのホスピタリティの知見をサービス現場に共有している。料理の品質だけでなく、説明や対話の設計まで実務として移植していく取り組み。
学術との結びつきも継続中。脳科学の研究者や自身が所属していた研究室の研究者らと進める共同研究では、食材を選ぶ場面で何が人の中で意識として立ち上がるのか(倫理的選好・より良い食選択)を明らかにし、その知見に基づき、どのような伝え方や提示がより良い食の選択を後押しできるかを検討している。研究の示唆を厨房で試し、その結果を再び研究に返す行き来を重ねている。現場の検証があるからこそ、理念が運用の手順にまで落ちる。
さらに、生江シェフは、ネットワークやコミュニティ全体の変化を志向する。下川教授の言葉を借りれば、「全員が完璧にサステナブルなレストランを作ろうとしなくてもいい。それぞれが、できることから始めることが重要」。すでに意識の高い人だけで、より厳しい制約を課すより、これまで意識してこなかった人が一つでも新しい実践を始める方がインパクトは大きい。ゼロかイチか、丸かバツかではない。生江シェフは、できていない点を責めるのではなく、できている点を持ち寄って称え合う横のつながりを重視し、アイデアを共有できる関係性づくりに力を注いでいる。

写真:レフェルヴェソンスのチームが揃って © L’Effervescence
おいしさと“良いこと”の両立
生江シェフは様々な活動において、料理の「おいしさ」を届けるのが前提と言う。人はまず感覚で判断するというのが理由。直感が満たされてはじめて、その先の理性的な理解が進む。正しさだけが先に立っても、本業である料理においしさの合意がなければ、社会をより良くするための提案は届きにくい。この前提に沿って、レフェルヴェソンスの実践は重ねられている。
食材を誰からどう仕入れるか、エネルギーの選択、循環的な器づくりの試み。年次のインパクトレポートで「どこが進み、どこに課題があるのか」を可視化し、次の一手に変える。サステナブルの先を見据える「リジェネラティブ」という視点や、輪島の椀、ガラスの再生といった取り組みも、この前提の上に、より良い選択を日々の営みのなかで具体化している。
東京という巨大な消費地から生まれる選択は、地域の生産環境にも波及する。積み重ねの影響を数値で確かめ、学術、産業、行政との協働で確かさを増していく。厨房から生まれる一皿は、個々人の心の中から外の世界、人々や自然へとつながっている。その認識が、ここでの実践を支えている。
現在地をどう捉えるかをたずねると、「つねに100%に近い状態だと思っていますが、ゴールに到達したと思った瞬間に景色が変わり、また次の探求が始まります」と答える。到達ではなく更新。この探求に終わりはない。次々に現れる障壁さえも楽しんでいるように見える。おいしさを核に、責任ある選択を積み重ねる。その繰り返しが、レフェルヴェソンスの現在地であり、これからの約束。

取材を通して、多層的な取り組みの背後に、生江シェフをはじめ、チームや関わる人々の不断の努力があることを強く感じた。持続や再生を見据えた実践を続ける生産者、そしてインパクトレポートの数字を日々、記録し続けること、その手間と覚悟は大きい。それでも続ける意義と価値があることを学んだ。私たちは「サステナブル」という言葉に耳慣れてきたが、解釈が十分に共有されていない局面もある。その先にある「リジェネラティブ」を考える機会をこの取材で得た。意識の高さの問題ではなく、社会の一員として、できることから少しずつでも行動を始めること。ときに“良いこと”は大変に感じられる瞬間もある。だからこそ、生江シェフが『おいしさが、なによりも人の心を動かす力である』と信じ、それを実践の起点に据える理由が腑に落ちる。自分自身も、その一歩を今日から積み上げたい。
(前編を読む)サステナブルのその先へ、レフェルヴェソンスが実践するリジェネラティブ・レストランの現在地 ― 前編
~ 三つ星とグリーンスターを併せ持つレストランが示す、新しいガストロノミーの形


生江史伸:1973年、神奈川県出身。北海道洞爺の「ミッシェル・ブラス トーヤ ジャポン」で腕を磨き、イギリスの「ザ・ファットダック」でもスーシェフを務めた。2010年に「レフェルヴェソンス」を開業。2012年版の初掲載で一つ星、2015年版で二つ星、2021年版で三つ星となった。2023年3月、東京大学大学院農学生命科学研究科を修了し、農学修士号を取得。
オープンから店を任される生江史伸氏は、早くして料理の道を志したわけではない。バンドマンだった慶応大学生時代、ジャーナリストを夢見ながら飲食店でアルバイトしたのがきっかけ。その後、「ミシェル・ブラス」の料理本に感銘に受けてフレンチに進んだ。北海道洞爺とフランスライオールの「ミシェル・ブラス」で研鑽を積み、自然界の植物を料理に取り入れる感性を磨いた。
写真:© Nathalie Cantacuzino / L’Effervescence
















