大阪有数のオフィス街、肥後橋。静かな路地の一角に「HAJIME」がある。レストランを率いるのは、米田肇氏。電子メーカーのシステムエンジニアを経て、幼いころより憧れた料理の世界へ身を置く。“料理の設計図”を書きおこし、緻密なまでに考えられた一皿に、テーマやストーリーを込める。その発想の原点、「食」が果たす未来について、米田氏に話を聞いた。

料理をする理由-食は希望
料理の原点は、春夏秋冬の食材を使った母の家庭料理。子供の頃、喧嘩や悔しい思いをして家に帰ると、そこには母が作る温かいご飯があり、泣きながら食べた。体の中に温かいものが入ると、また頑張ろうという気持ちになり、料理が心のよりどころになったと振り返る。日々、料理上手な母の料理に触れることで、食に対する興味が生まれ、米田氏の味覚のベースとなった。「いつも思うことは、お客様の心の温度を1℃でもあげたい。食ができる一つの大きなことだと思います」。
その思いを彷彿とさせる、店でのエピソードを明かしてくれた。会社が倒産して、まさに最後の晩餐と「HAJIME」を訪れた夫婦。人生の岐路、食事を終えたご主人が発した言葉は、「お母さん、もう一度やってみよう」。その後、会社を立て直したと米田氏が耳にしたのは何年か経ってから。「私たちは裕福ではないし、料金も高いのに、今でもなぜここに来るのか分かる?それは、あの時の料理に救われたからですよ」と打ち明けられたという。料理に携わってきてよかったと思える瞬間。まさに“食は希望”と語る米田氏。人の心を動かす力、料理の可能性を感じた。

料理は最高のエンターテインメント
「私たちは多くの感覚器をもっています。例えば、映画や演劇、芸術作品では、味覚を使いませんが、料理は全ての感覚を使うことができる。そういう意味で、最高のエンターテインメントになる条件が揃っているのです」。これは、単に味や香り、美しさだけでなく、料理を口に運んだときの音や触覚、器を持つときの温かさや感覚に至るまで、一つ一つのコンセプトをどこまで深く考えられるかが重要。またコースの流れでは、歌詞にメロディをつけるように、前後のバランスで抑揚をつける。テーマと料理がピッタリ合うことで、「HAJIME」を訪れるゲストに感動が生まれるのである。

言語化、数値化してチームへ共有
米田氏が修業時代に一番困ったことは、調理方法の伝え方。例えば、大体こんな感じと言われて、1.5cmに切ると、それでは大きい。では何センチですか?といったやり取りを繰り返していたとか。その経験から、スタッフと共有するためには、言語化、数値化をする必要があると考えた。ミリ単位まで詳細に示し、料理の完成度を90%まで近づける。食材は同じ産地でも味に違いがあり、分量だけでは測れないため、最後の仕上げは感性で微調整をする。その味の複雑さをいかにコントロールして、バランス良く仕上げるかがポイントだという。
料理の設計図
「料理人の中には、冷蔵庫をさっと開けて、感性で料理を作る人もいますが、僕はそれができない。なぜおいしいのか?どうしてこれが良い状態なのか?と考えながら、ゆっくり構築していくので、建築家みたいな考え方なのです。設計図があるからこそブレない。感覚だけに頼っていたら、その日の調子で影響される。料理人もアスリートと同じで、年を重ねると体力も落ちていく。でもそこは、チームプレーでカバーできれば、体力に頼った作り方をしなくていいわけですよね」。学生時代には、絵画コンクールで入賞するほどの画才を持つ米田氏。直筆で書かれた料理のレシピは、まるで設計図のよう。米田氏がイメージする世界、一皿に秘められたテーマを、誰もが共有できるのもうなずける。

食の未来へ向けて
「社会構造の合理化が進み、ロボットやAIで生産性が向上しても、働き手がいなくなるような社会になる。それに対して、私たちは人を雇用し、人を育て、共に成長し、人との関係性を作っていく産業。食は環境や社会問題にも密接に関連していて、未来の社会システムを構築する上での鍵になります」。食の未来へ向けて、飲食業が抱える問題点について、積極的に業界全体へ働きかける活動も行っている。例えば、コロナ禍で苦しむ飲食店の支援を国に求め、署名活動の先陣を切った。わずか2日で5万人、最終的には18万人もの署名が集まったという。様々な課題は、単に日本だけの問題ではないと、その視線を海外にも向けはじめている。
長時間労働、休日が少ない、給料が安いと言われ、料理人になることを父から反対された料理の世界。
「飲食業界に恩返しができるように、少しずつ労働環境を変えていき、良い業界になったよと話せるようになりたいですね」と笑顔で語った。
これまで到達点に対して徹底して考え、実行に移してきた米田氏。“食は希望”であり続けるための挑戦は続く。

関連のあるお店を検索:
「HAJIME」
関連記事を検索:
アジアのトップシェフによる2022年ハイライトと2023年の展望
アジアのミシュランスターシェフによる「2023年レストラン業界5つのトレンド」


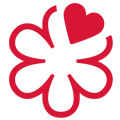












%20-%20Aman%20Nai%20Lert.jpg)
