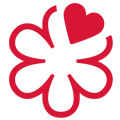「明寂」は、哲学者の山口諭助が唱えた「明る寂び(あかるさび)」から。寂びた風情を残しつつ、そこはかとない華やかさがあるという意味合い。「ミシュランガイド東京 2023」では初掲載で二つ星に。そして三つ星へと駆け上がった。わずか数年でミシュランガイドにおける最高の評価を得た明寂とは。ミシュランガイドインスペクター達の視点から探る。

屋号、内装、もてなし
控えめな「明寂」の看板、 静寂な階段を下りると、屋号を記した行灯が目に入る。書家、加山幹子が書きしるした、明と寂の書は、「光と影」に美を見出したような趣。京都の建築家が手掛けた数寄屋の意匠。一枚板のカウンターを設え、革張りの椅子がゆったりと配される。席から見えるのは土壁に飾られた一輪挿し。千利休の「朝顔の茶会」を連想させるような、削ぎ落しの美学。一切の装飾を省き、研ぎ澄まされたような空間に凛とした空気が満ちる。簡素な中の深遠な美、静寂と内面の豊かさ。建築、器、料理、もてなし、すべてに精神が伴う。先ずは、中村英利による一期一会の精神をもって挨拶が交わされる。そしてチームスタッフは唯一無二の機会に、もてなしの心を尽くす。関連記事:ミシュランの星付きレストランとは?


料理
料理で大切にするのは“調和、淡、清らか”なこと。森、川、海に恵まれた日本の地理が育んだ食材。自然を調和し、淡い味の真味を引き出し、清く純粋な水を用い表現する。それらは、京都宮津湾から取り寄せる海底湧水を用い料理(ことわりをはかる)。理をはかるとは本質を理解すること。食材、調理、もてなしの理には、おいしさに留まらず、自然の摂理や客人への敬意といった精神性も重んじている。大根の潮煮
献立の始まりは野菜の潮煮から。器の中には、いちょう切りにした大根と煮汁のみ。海水の塩分で大根の自然な甘みを引き出す。素朴ながら潔い盛り付けが印象を深める。
真鯛とあおりいかの造り
明石の鯛は薄く引き、鯛だしの割り醤油で食す。あおりいかは細かく包丁目を入れ、いかの粉末を合わせた塩で味わう。一つの食材を異なる調理で仕上げ自然な風味を循環させ一品に集約。巧みな包丁技術と豊かな発想が生きる。

貝寄せの煮物椀
春を告げる貝を使ったお椀。蛤、しじみの胡麻豆腐を椀種に。白あわび茸を貝になぞらえ、あしらいとするのが風流。黒漆椀に映える白い吸い地は、海水と貝類によるコハク酸の旨みが重なる。素材と水を表現するため、椀物に昆布と鰹節を使わないのが理念。
わかさぎの絹巻寿司
絹巻寿司は献立に欠かさない一品。この日の魚はわかさぎ。器には、絹に見立てた薄焼き玉子を敷く。酢飯に合うよう、米を食べて育った鶏の卵を使用。黄身まで白く、絹の白色を表現している。その上に酢飯、揚げてから焼いたわかさぎの身を巻いて味わう。清浄かつ無垢な純白はまるで和紙の様。日本の歴史において奉書や懐紙は大切なものを包む意味合いを持ち、伝統文化や美意識をも連想させる。

潮蕎麦
蕎麦つゆに海水を用いることから潮蕎麦と名付けた。先ずは火を入れた宮津湾の海底湧水を少し口に含み、自然の甘みと旨みを楽しむ。蕎麦は細打ちの十割。海水につけて食すと蕎麦の風味が一層引き立つ。
感想
食材や調理に対し、なぜ?どうして?と常に疑問を巡らせ、自らの答えを導き出す中村英利。また、食材の産地に訪れた際、水と共に生きていることを実感したという。四方を海に囲まれた日本、国土の大半は豊かな里山。そこから流れる川の水と肥沃な土、そして海へ流れる水を食材と結ぶように料理を考案する。それらの循環は、太陽や月を含む天体的なものでもあり、自然の育みでもある。明寂の料理には、日本の水の豊かさが秘められている。中村英利が言う「水に記憶を残す」と共に、空の色や風の香りをも感じさせる。サン=テグジュペリの「星の王子さま」の至言に「本当に大切なものは、目には見えない」の行がある。物質的なものや表面的なものではなく、心で感じるつながりや価値。料理をいただいていると、自ずとすべてに感謝したくなるような、自然に生かされているような明寂の日本料理。さあ、地球に生きる人類は何をする!おいしいだけではなく、そのようなことを気付かせてくれる体験であった。Top Image: © Myojaku